そろそろ台湾が恋しくなってきたので、侯孝賢(ホウ・シャオシェン)監督の作品を見ることに。香港映画とか韓国映画とかなら馴染みもあるのですが、台湾映画を観るのはこれがはじめて。前回、台湾を旅行したのが2019年の夏ですから、もうすぐあれから2年になるんですね。今思うとギリギリで行けて良かった。映像を通して、台湾の美しい自然を回想しながら視聴しました。(早くまた行きたい…)

「仰げば尊し」ではじまり、「赤とんぼ」で終わる映画。台湾の田園風景もどこか日本的だし(さすがに水牛はいないけど)、懐かしさがあふれます。意地悪したり、悪さしたり、反抗してみたり、そうかと思えばちょっと大人っぽく背伸びをしてみたりと、多感な思春期の少年、冬冬(トントン)の一夏の物語。

制作費は全然かけていないけれども、子役をはじめ、演技がものすごく上手い。また侯孝賢監督のカメラワークや間の取り方が絶妙でして、見終わったあと、しばらく余韻に浸ってしまいました。

この時代の台湾の地方の暮らしや農村の貧富の格差なんかも分かり面白かったのですが、とりわけ台湾の折檻の仕方が恐ろしいんです。冬冬(トントン)の叔父さんがどうしようもない大人なのですが(笑)、厳格なおじいさんを怒らせたときがすさまじい。まあ昭和の日本もこんなんだったのかな?

侯孝賢がデビューしたての時の映画でして、日本では全然知られていないのですが、個人的には『冬冬の夏休み』よりも気に入りました。
田舎に赴任してきた先生と教え子達を主人公にした青春映画。映像の中の子供達が実に生き生きとしているのが印象的。川遊び、喧嘩、家出、転入生、お仕置き、初恋と、日々様々な事が起こります。そんななか家族愛があったり、ぶつかり合いながらも成長があったりと、起伏のあるストーリーが見る者を画面に釘付けにします。
本作で女性教師の役を演じた台湾のアイドル歌手、江玲の主題歌がまたいい。優しい感じのメロディーが台湾の田舎の風景によく似合います。

映画は町から来たディーゼルカーを子供達が追いかけるシーンではじまり、町へと帰るディーゼルカーを追いかけるシーンで幕を閉じる。これがなかなか印象的。(ちなみにこのディーゼルカーは1930年ぐらいから走っていた、日治時代のもの。)
ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞し、侯孝賢監督を世界的に有名にした作品。個人的に最も気になっていたのですが、テーマが重いので、三作のうち最後に視聴。
映画は1945年、昭和天皇の玉音放送からはじまり、1949年の蒋介石による台北臨時政府の樹立までの間の台湾の混迷を、林(リン)一族を通して描き出します。台湾近現代史の最大のタブー、二二八事件を正面から取り上げているだけあって、当時は公開すら危ぶまれたそうです。

これからの台湾について嬉々として語り合う若者達。そんななか、雷鳴がとどろき、歌声をかき消してゆくあたりが、映画の展開を暗示しているようでつらい。
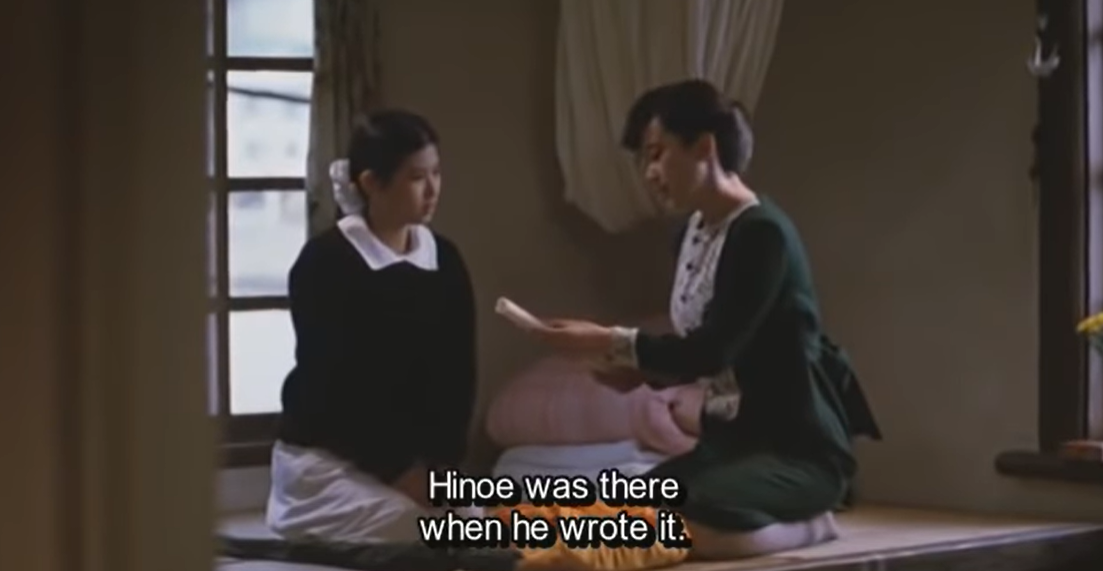
映画には日本人も何人か登場します。そうですよね、日本領ではなくなったとはいえ、すぐ引揚げたわけではないのだから。前2作もそうですが、ストーリーを紡ぎ合わせて物語を重層的にするのが、侯孝賢監督の腕前だなぁと感じました。女の子が、台湾人の恋人の妹に着物を託す話には思わず目がジーンとなってしまった。

林家は4人兄弟。四男の文清は写真家だが、耳が聞えず話せない。演じている役者は若き日の梁朝偉(トニー・レオン)なんですよね。細かい仕草を含め、演技が素晴らしい。特に文清の友人の妹、寛美との言葉はないけれども賢明なやり取りは美しすぎる。

終戦直後の喜びもつかの間、汚職、インフレ、失業、インテリ層に対する弾圧から市井の人の間で、私利私欲に走る国民党政権に対する不満が募り出します。これが一気に吹き出したのが台北で起こった二二八事件。国民党政権は全土に戒厳令を敷き、庶民の暴動を武力で押さえ込もうとします。最終的に亡くなった人数は数万にも及ぶのだとか。

庶民の側も抵抗します。「あんた、どこからきた」と台湾語と日本語で聞き、分かれば本省人(台湾人)、分からなければ外省人(戦後、中国本土から来た国民党政権側の人)と区別するシーンは緊張が走ります。

やがて、国民党による弾圧の触手は林家にも忍び寄ります。

『悲情城市』を日本語にすると「悲しみの街」。タイトル通り、救いようのない悲劇です。それにもかかわらず、ただ淡々と進む物語がいっそう悲哀感をかき立てます。
おそらく観る人に特定の感情を押しつけないよう、侯監督があえて意識したのでしょう。歴史を生きた人々の記録といったほうがいいかもしれない。二二八事件を直接批判するわけではなく、また特定の一人にスポットライトを当てるわけでもない。この映画は混乱の時代を生き抜いた一般庶民の生活の記憶を留めた、1つの芸術作品のように感じます。
一番分かりやすいのが、玉音放送に始まる映画の幕開けのシーン。敗戦という、歴史が大きく揺れ動いているにもかかわらず、林家は出産さわぎでバタバタといそがしい。二二八事件もそう。国民党の弾圧を直接描き出すわけではなく、台北郊外の平和な林家に、徐々に影が迫る様子を描き出す・・・。
とても印象に残る映画でした。もっとも、自分は台湾の歴史について知らないことが多すぎた。それに本作は、一度観ただけではどうにも理解できた気がしない。とくに台湾語、日本語、北京語、上海語、広東語と、さまざまな言語が作中で飛び交っており、その意味するところやニュアンスなんかは、自分には到底分からない。なかなか難しい映画なので、そのうち改めて見直そうと思います。
このあと、蒋介石による白色テロルといわれる恐怖政治が始まったわけですが、二二八事件はそのはじまりであり、長らくタブーとして封印されてきたそう。そういえば台湾高雄市の歴史博物館で2階のフロア全部を使って二二八事件を取り上げていましたが、当時はよく知らなかったので、ちゃんと調べてから行けば良かったなぁとつくづく。侯孝賢自身は外省人のルーツだということで、あえてこのテーマに取りかかるのは、相当大変だったでしょう。すごく考えさせられる映画でした。